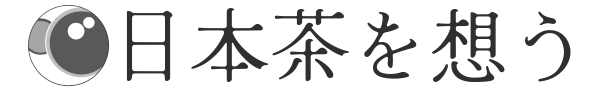ゴールデンウィークと言えば、お茶業界では新茶の季節。2024年5月4日、人生で初めてのお茶摘み体験へ行ってきました。正直、お茶屋さんで働くまではお茶摘みとか新茶とか、全く気にしたことがなかったのですが…身近になると、一度くらいは経験してみたい!という思いがふつふつと湧いてきて、思い切って行ってみることにしました。
伺ったのは、埼玉県狭山市の「浅見園」さん。お茶摘みの体験ができるお茶屋さんはたくさんあってどこも魅力的でしたが、調べに調べた結果、何となく雰囲気が私に合ってそうな気がした浅見園さんに決めました。この日は天気がとても良くて、茶摘み日和。
到着してまずは、外のテーブルで楽しく美味しいひと時。
自分で抹茶を点てて、柏餅をいただきました。抹茶の甘みが柏餅に合います。

次は煎茶を淹れます。持ち手のない急須、宝瓶(ほうひん)は初めて見ました。高級感があります。

最後はお茶の葉の天ぷら!
抹茶用に栽培されたものと煎茶用に栽培されたもの、2種類のお茶の葉を用意してくださいました。抹茶用の方が少し緑が濃く艶があります。作り方は簡単、衣にくぐらせて油に入れるだけ。すぐに出来上がります。
こちらは子供たちに作ってもらいました。

どちらの葉も苦みはほとんどなく、サクサク食感でとってもおいしい。どちらかというと、抹茶用の方がクセが少なく食べやすい感じがしました。被覆栽培によって甘みが強くなっているということなのでしょう。
この季節だけの贅沢な味。いいお天気の日に外で食べるというのが最高でした。
美味しい時間のあとは、製茶工場の見学です。
工場の入り口には摘んだばかりのお茶の葉がコンテナに山積みになっていました。触らせてもらうと熱を発しているのがよくわかります。湿気などで葉が痛まないように、コンテナには送風機能が付いているそうです。
この時間機械は動いていなかったのですが、作業の流れに沿ってすべての機械を丁寧に説明していただき、一つ一つ中をのぞかせてもらったりしてとても勉強になりました。
そしていよいよ!本命のお茶摘みです。青空と一面のお茶。清々しい景色です。

生き生きとしたお茶の葉を丁寧に摘んでいきます。はじめは緊張していましたが、慣れてくるとどんどん進みます。
籠にたくさん摘んで大満足です。

茶畑の一部では被覆栽培も行われていました。玉露やかぶせ茶、碾茶はこのような栽培方法になります。

一定期間光を遮ることで葉の色は濃く鮮やかになります。味は甘味やうま味が強くなり、煎茶とは違った味わいになります。
帰りの車の中では、ずっと悩んでいました。たくさん摘んだお茶の葉をどうしようかと。
天ぷらにするか、お茶作りに挑戦するか、何か料理に使ってみるか…
お茶摘みを満喫して疲れていましたが、そのまま放っておくと酸化発酵してしまうので、帰ったらもうひと頑張りしなくては!と気合を入れ直していました。